

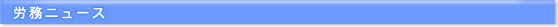
| 第8号 働き方改革について その2 | 2018-02-26 |

~はじめに~
働き方改革に関する書籍を読んだり、講演やセミナーに参加すると、前回お伝えした長時間労働の是正と同じくらい大きく取り上げられているのが
「同一労働同一賃金」についてです。
同一労働同一賃金とは何ぞや、という考え方や概念については、実に様々な意見が展開されています。この概念については改めて触れるとして、今回は政府が言う同一労働同一賃金について、法改正の内容と併せてお話したいと思います。
~政府の目指す同一労働同一賃金とは~
【同一労働同一賃金ガイドライン案前文より抜粋した目的】
・正規・非正規に関わらない均等・均衡待遇を確保し、同一企業・同一団体における正規と非正規の間にある不合理な待遇差の解消を目指す
正規:無期雇用フルタイム労働者を指す
非正規:有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者を指す
同じ会社で同じ仕事をしているのであれば、正社員・契約社員・パート・派遣いずれの雇用形態であっても同じ水準の待遇にすることを「同一労働同一賃金」として表しています。
この目的を達成するために、政府は以下3つの法律改正を行おうとしています。
~改正法案要綱からみる同一労働同一賃金~
【労働契約法の改正】
・20条(不合理な条件の禁止)の規定を削除
20条:有期契約労働者と無期契約労働者の間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を禁止する
→改正後のパート・有期労働法および労働者派遣法に同様の内容を移行
【パートタイム労働法の改正】
・適用対象にパートタイマーの他、有期雇用労働者を含めた(法律の名前を改正)
・不合理な待遇の禁止
→労働契約法20条にあった規定をパート・有期全体に適用
<法律案要綱より案文を抜粋>
事業主は、この雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与、その他の待遇の「それぞれ」について、当該待遇に関する通常の労働者との待遇の間において《中略》当該待遇の「性質」および当該待遇を行う「目的」に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない
→総合的に不合理がないかを判断するのではなく、「それぞれ」個別に判断する
→手当ひとつひとつに対し、どういった「目的」で支払っているのか、明確にし、吟味することが必要となる
・労働者から求めがあったときは、通常の労働者との間の待遇の相違の内容および理由について、説明しなければならない
→説明をした時、労働者が納得できる合理性が必要
【労働者派遣法の改正】
・派遣先の会社は、派遣元に自社の通常の労働者に関する待遇の情報を提供しなければならない
→派遣先の正規労働者と、派遣労働者の均衡を図るため
・不合理な待遇の禁止
→労働契約法20条にあった規定を派遣労働者にも適用
→パート・有期と同様、待遇ひとつひとつに対し合理性を個別に判断する
<合理性の判断基準となるもの>
a派遣先の通常労働者の待遇:派遣先からの情報提供に基づき、派遣先との均衡を図る方式
b派遣労働者が従事する業務と同様の業務に就く一般労働者の平均待遇:派遣元で労使協定を締結することで、広く一般労働者との均衡を図る方式
→平均額は、業務別・地域別で出されることが予想される
・労働者から求めがあったときは、通常の労働者との間の待遇の相違の内容および理由について、説明しなければならない
→説明をした時、労働者が納得できる合理性が必要 ※パート・有期と同様
これまで、無期フルタイムと有期フルタイムの間で規定されていた不合理な条件の禁止の対象をパート・派遣にも拡げています。さらに労働者への説明義務も法に定めています。
~おわりに~
同一労働同一賃金ガイドライン案では、正規・非正規の間に存在する待遇差について、賃金のみならず福利厚生・キャリア形成なども含め、問題となるもの・ならないものを具体例で列挙し説明がなされています。しかし内容は曖昧で、特に基本給については問題となるもの・ならないものの違いがわかりにくく、実務的にやりにくいと感じるのが正直なところです。
また、言い回しによって合理的にも不合理にも解釈ができ、労使が争う事例が増える可能性も考えられます。そして、客観的に見て十分に合理性があると言える制度を作るためには、大きな改革をせまられる会社もでてくると予想されます。
正規と非正規の間だけではなく正規と正規の間でも、年功序列の賃金体系の場合などは同じ仕事をしているのに待遇差が生じていると解釈されるケースもでてくるかもしれません。
「同一労働同一賃金」を達成するには、こうしたクリアすべき課題がたくさんあるのです。
国会では、裁量労働制に関連するデータが不適切であった問題も議論されており、働き方改革関連法案の行方についてしばらく目が離せない状況となりそうですが、今後どのように進んでも、予測できる範囲での準備はしておきたいところです。
そう考えるとまずは今、ご自身の会社が支払っている給与体系を改めて見つめ直してみる必要はありそうです。